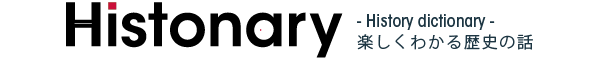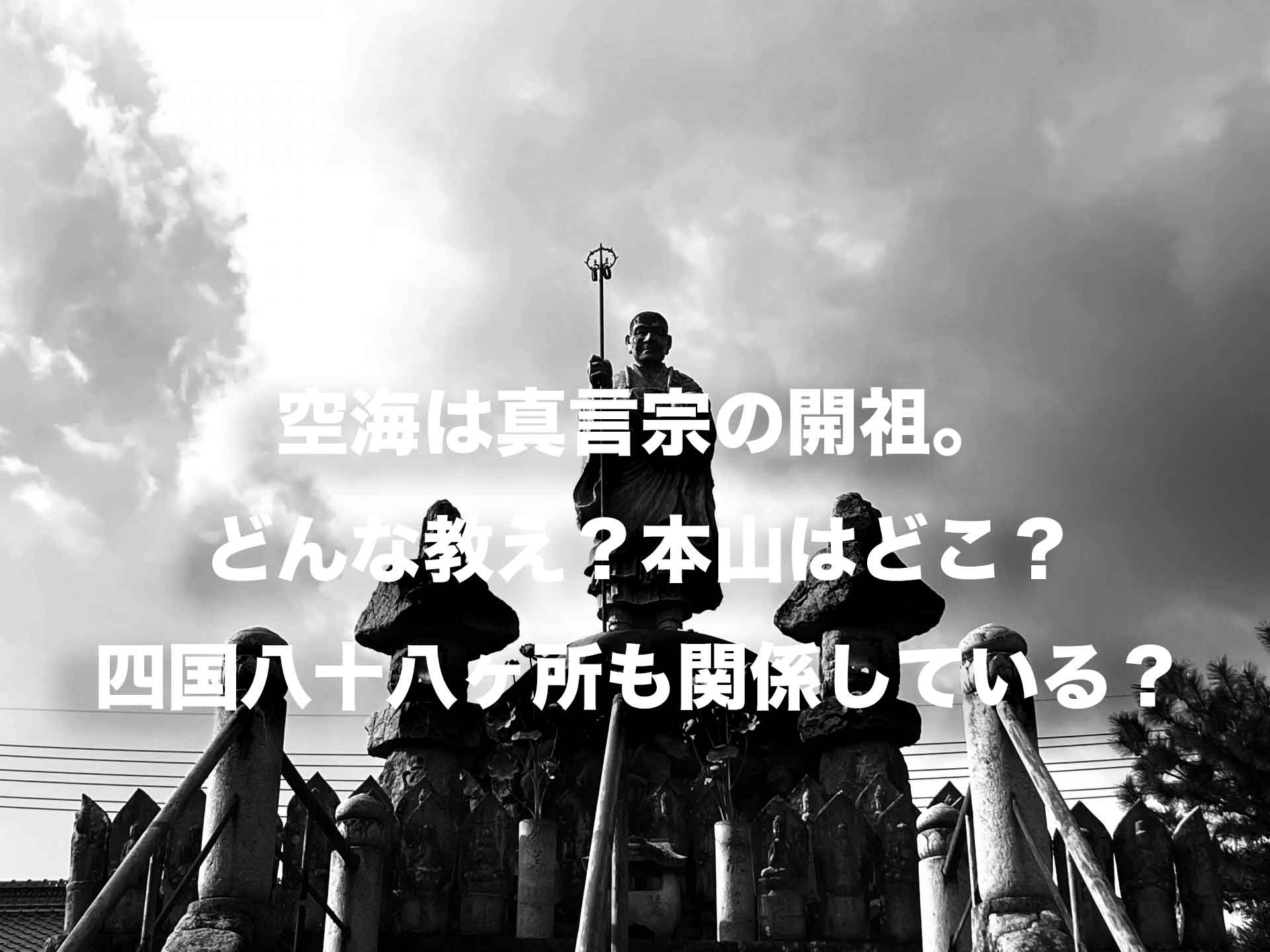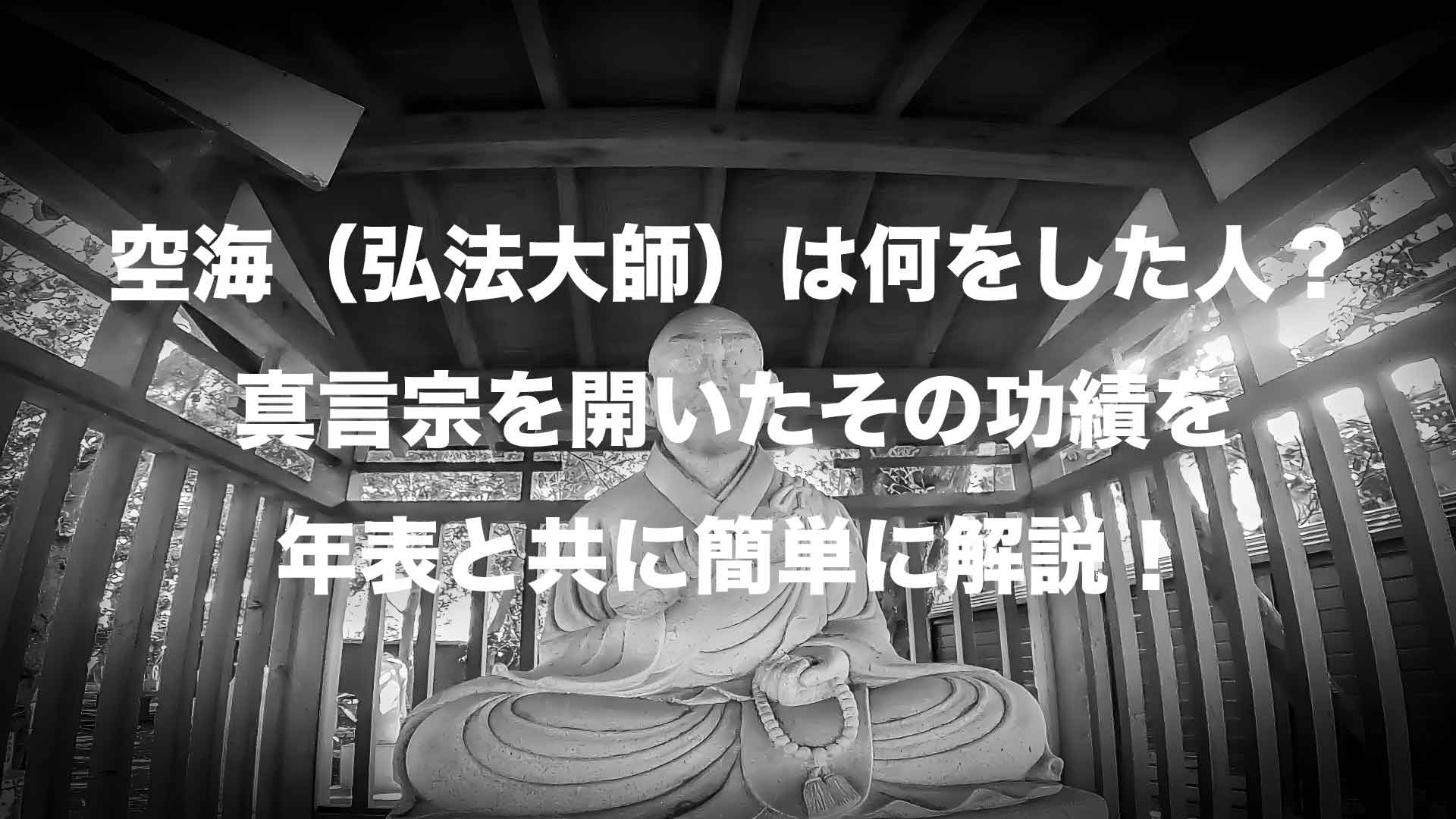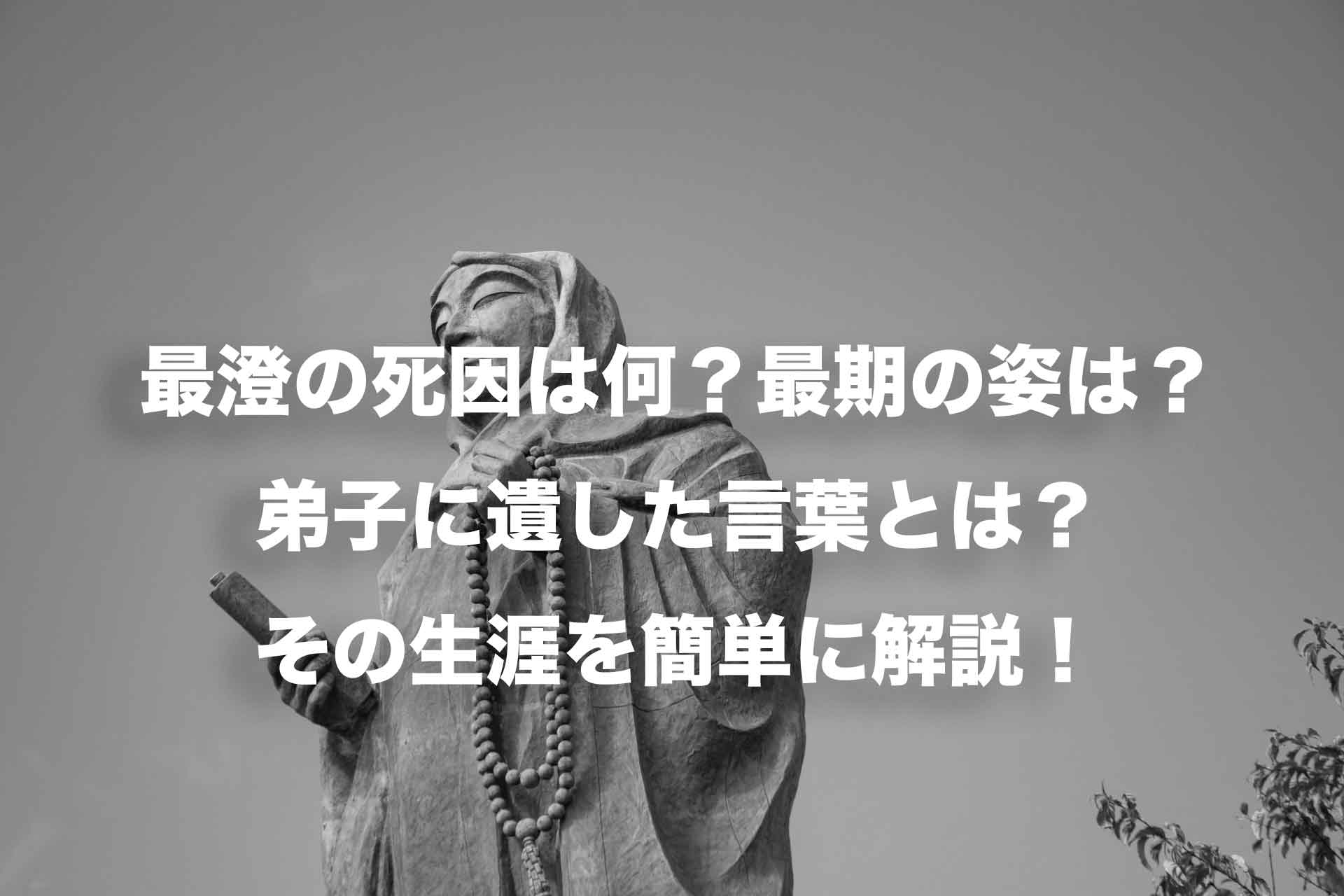清少納言の枕草子とはどんな内容?いつ書かれた?現代語訳など簡単に解説!
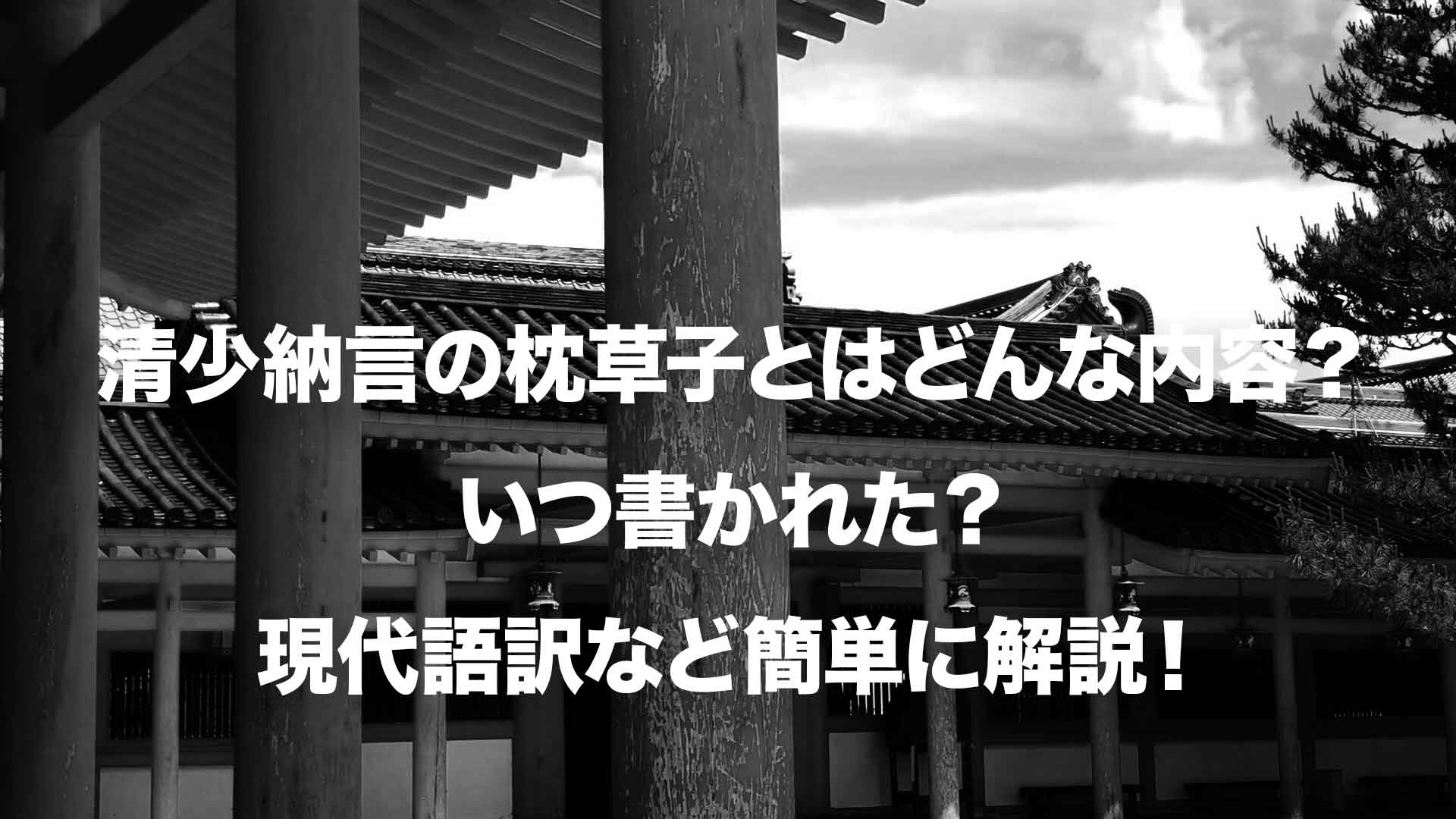
清少納言(966(康保3)〜1025(万寿2))は、平安時代中期に活躍した歌人・作家です。
2024年の大河ドラマ『光る君へ』では、ファーストサマーウイカさんが演じられることでも話題となっています。
そんな清少納言が書いた有名な作品の1つに『枕草子』というものがあります。
この枕草子とは、どのような内容のものなのでしょうか?
この記事では、清少納言の枕草子について簡単に解説していきます。
目次
清少納言の枕草子はどういう内容?
清少納言の有名な作品の1つに『枕草子』というものがあります。
学校の授業で習ったことがあるという人も多いのではないでしょうか?
ここでは、その清少納言の枕草子について簡単に解説していきます。
清少納言の枕草子はいつ書かれた?
清少納言の枕草子が書かれた正確な時期は判明していないのですが、1001年(長保3年)頃にはほぼ完成していたと推測されています。
また、同時代の有名な作品には、紫式部の『源氏物語』があり、時代が近いことからよく対比して語られることがあります。
「随筆」というジャンルの作品であり、その当時の清少納言の何気ない日常のことがたくさん描かれています。
ちなみに、「枕草紙」「枕冊子」「枕双紙」「春曙抄」とも表記されていることもあります。
清少納言の枕草子の内容は大きく分けると3種類に分かれている
清少納言の枕草紙は、約300の章段から成り、大きく分けると下記の3種類に分類されます。
1、「虫は」「木の花は」「すさまじきもの」「うつくしきもの」などと言ったものに代表される「ものづくし」の類聚章段
2、日常生活や四季の自然を観察した随想章段
3、清少納言が出仕していた定子周辺の宮廷社会を振り返った回想章段(日記章段)
この3つの中でも特に特徴的なのが、類聚章段です。
ここは、他の文学作品に類を見ないくらい同じ種類の事柄を集めた章段となっています。
名詞がひたすら綴られていくのですが、その言葉選びから、清少納言の鋭い感性や、知性の高さが伺える文章となっています。
清少納言の枕草子の内容の特徴は?
清少納言の枕草子は「随筆」というジャンルの作品になります。
そのため、内容は基本的に清少納言の身に実際起こったことや、清少納言自身が感じたことなどを中心に書かれています。
また、同時代の文学作品には、源氏物語があるのでよく比較されます。
源氏物語は「あはれ」の文学であると言われるのに対して、枕草子は「をかし」の文学であると言われています。
ここでの「をかし」とは、清少納言の独特の美的感覚を指します。
私達は朝焼けや夕暮れ、蛍が飛び交うのを見ると、「あぁ、きれいだなぁ」と感じて終わる人がほとんどでしょう。
しかし、清少納言はそれを一度頭で考えて、知的な美や楽しみを見出し表現しているのです。
このように、清少納言の知性の高さを感じることができる、それが枕草子なのです。
清少納言の枕草子は日本三大随筆に選ばれている?
清少納言の枕草子は、日本三大随筆の一つに選ばれています。
枕草子以外の日本三大随筆は以下の2つです。
- 鴨長明『方丈記』(鎌倉時代初期)
- 兼好法師『徒然草』(鎌倉時代末期)
また、清少納言の枕草子は「日本最古の随筆」「世界最古のエッセイ文学」とも言われています。
それほどまでに枕草子は、当時の宮廷生活などを知るのに貴重な資料であり、たくさんの人々が時代を超えて感銘を受けた作品だと言うことですね。
清少納言の枕草子に関するエピソードとは?
日本三大随筆にも選ばれるくらい有名な枕草子ですが、実は元々公表される予定はなかったと言われており、様々なエピソードが存在しているのです。
ここでは、清少納言の枕草子に関するエピソードを簡単に解説していきます。
清少納言の枕草子執筆動機は定子だった?
清少納言が枕草子を書き始めたきっかけをくれたのは、中宮・定子でした。
定子は清少納言が仕えていた人物で、2人は主従関係でありながら非常に仲の良い関係でした。
ある日、内大臣の藤原伊周が定子と一条天皇に、当時まだ高価であった紙を献上しました。
その際に、定子は「帝の方は『史記』を書写されたが、こちらは何を書こうか」と清少納言に問いかけます。
そこで、清少納言が「枕にこそは侍らめ」と即答したため、定子は「ではお前に与えよう」と言ってそのまま紙を与えたのでした。
(ここでの、「枕」の意味は、寝具の枕ではなく、「歌枕」などの書物を意味するのではないかと考えられていますが、真相ははっきりとはしていません)
そして、与えられた紙に、清少納言が枕草子を書き始めたのでした。
このエピソードから、「枕草子」という作品名になったと言われています。
なお、枕草子を書くきっかけとなった定子ですが、紙を渡した数年後、24歳という若さで亡くなってしまいます。
そのため、定子が枕草子の全編を読むことができたのかどうかはわかっていません。
清少納言の枕草子は最初はこっそりと書いていた?
定子に紙をもらって枕草子を書き始めた清少納言でしたが、実は最初は誰にも公表すること無く、こっそりと書いていました。
なぜならば、この枕草子を書き始めた当初、清少納言は宮中での様々なことが重なり、絶望し出家してしまっていたのです。
そして、宮中から身を引き、家に引きこもっていました。
定子と清少納言は非常に仲が良かったので、定子は引きこもってしまっている清少納言に戻ってきてほしいとひたすらラブコールを送り続けます。
その過程で大量の紙も贈っていたと言われています。
この際、定子自身もあまりよくない状況だったため、清少納言は定子を慰めるためにと筆を取ったのです。
枕草子はそうして、定子にだけ見せる予定のものだったというわけですね。
しかし、左中将だった源経房が清少納言の家を訪れた際にこの本に気づき、その内容の素晴らしさから、本を借りて、それを周囲の人間にも読ませたのです。
こうして、こっそりと書いていたはずだった枕草子は、あっという間に世間に広まっていったのでした。
清少納言の枕草子の現代語訳は?
清少納言の枕草子は、平安時代の文学作品ですから、当然当時の言葉で書いてあり、現代の私達が読んでもすぐに内容が入ってこないかもしれません。
しかし、現代語訳を見ると現代のSNS的な内容のことが書いてあったりすることがわかります。
ここでは、清少納言の枕草子の現代語訳を簡単に解説していきます。
清少納言の枕草子の有名なのは冒頭部分?
清少納言の枕草子で一番有名な箇所は、教科書などでも取り上げられることの多い冒頭部分です。以下、その現代語訳です。
【枕草子の原文】
春はあけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎはすこしあかりて、むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。
夏は夜。月のころはさらなり、やみもなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。雨など降るもをかし。
秋は夕暮れ。夕日のさして山の端いと近うなりたるに、からすの寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど飛び急ぐさへあはれなり。まいて雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入りはてて、風の音、虫のねなど、はたいふべきにあらず。
冬はつとめて。雪の降りたるは、いふべきにもあらず、霜のいと白きも、また さらでもいと寒きに、火など急ぎおこして、炭もてわたるも、いとつきづぎし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も白き灰がちになりてわろし。
【枕草子の現代語訳】
春はあけぼの(がよい)。じょじょに白くなっていく山ぎわが少し明るくなって、紫がかった雲が細くたなびいている(その景色がよい)。
夏は夜(がよい)。月が明るいころは言うまでもなく、闇のころであっても、ほたるが飛びちがっている(その光景がよい)。また、ただ一匹二匹などと、ほのかに光って飛んで行くのも趣がある。雨などが降るのもよい。
秋は夕暮れ(がよい)。夕日がさして山の端にたいへん近くなっているところに、からすがねぐらへ行こうとして、三羽四羽、二羽三羽などと飛び急ぐ、そんな様子さえもしみじみとした情趣ががある。まして、雁などの連なって飛んでいるのが、非常に小さく見えるのは、たいへん趣が深い。日が暮れてから聞こえてくる、風の音や虫の声なども、また言うまでもないことである。
冬は早朝(がよい)。雪が降っている朝は言うまでもなく、霜がたいへん白い朝も、またそうでなくても、非常に寒い朝に火などを急いでおこして、炭を持って運びまわるのも、たいへん似つかわしい。(しかし、)昼になって、寒さがゆるんでくると、火桶の火も白い灰がちになってよくない。
少納言の枕草子の他の箇所の現代語訳は?
冒頭部分以外にも清少納言の知性の高さを感じられる箇所はたくさんあります。
ここでは、その一部を簡単にご紹介していきます。
枕草子 第二十六段:
(原文)
心ときめきするもの。
雀の子飼ひ。稚児遊ばする所の前渡る。
よき薫き物たきて、一人臥したる。唐鏡の少し暗き見たる。
よき男の車どとめて、案内問はせたる。
頭洗ひ、化粧じて、香ばしう染みたる衣など着たる。
ことに見る人なき所にても、心のうちはなほいとをかし。
待つ人などのある夜、雨の音、風の吹きゆるがすも、ふと驚かる。
(現代語訳)
心がときめくもの。
スズメの子を飼う。赤ん坊を遊ばせている所の前を通る。
良い香りをたいて、一人で横になっているとき。舶来の鏡が少し曇ったのを覗き込んだとき。
身分の高そうな男が牛車を止めて、供の者になにか尋ねさせているの。
髪を洗い、お化粧をして、香りをよくたきこんで染み込ませた着物などを着たとき。
別に見る人もない所でも、心の中ははずんでとても素敵だ。
待っている男のある夜、雨の音、風が吹き、がたがた音がするのも、はっと胸が騒ぐ。
枕草子 第二十七段:
(原文)
過ぎにし方恋しきもの。
枯れたる葵。雛遊びの調度。
二藍、葡萄染めなどのさいでの、押しへされて、草紙の中にありける、見つけたる。
また、折からあはれなりし人の文、雨など降り徒然なる日、探し出でたる。
去年のかはぼり。
(現代語訳)
過ぎ去った昔が恋しく思い出されるもの。
枯れてしまったアオイの葉。人形遊びの道具。
紫がかった青色、薄紫色などの布の端切れが、押しつぶされて本の間なんかに挟まっているのを見つけたの。
また、もらったときしみじみと心を動かされた手紙を、雨などが降ってすることのないような日に見つけだしたの。
去年の夏の扇。
枕草子 第三十九段:
(原文)
あてなるもの。
薄色に白襲(しらがさね)の汗袗(かざみ)。
雁の子。削り氷のあまづらに入れて、新しき鋺(かなまり)に入りたる。
水晶の数珠。藤の花。梅の花に雪の降りかかりたる。
いみじう美しき児の、いちごなど食ひたる。
(現代語訳)
上品なもの。
薄紫の衵(あこめ)の上に白いかざみをかさねたの。
カリの卵。かき氷に甘いつゆをかけて新しい金の器に入れたの。
水晶の数珠。フジの花。ウメの花に雪が降りかかっているの。
とても可愛らしい子供がイチゴなどを食べているの。
枕草子 第五十九段:
(原文)
河は。
飛鳥川、淵瀬も定めなく、いかならむと、あはれなり。
大井川。音無川。七瀬川。
耳敏川、またも何事をさくじり聞きけむと、をかし。
玉星川。細谷川。五貫川、沢田川などは催馬楽などの思ははするなるべし。
名取川、いかなる名を取りたるならむと、聞かまほし。
吉野川。天の河原、「棚機つ女に宿借りらむ」と、業平が詠みたるも、をかし。
(現代語訳)
川は。
飛鳥川、昨日は深かったところが今日は浅瀬になっていると、歌では無常そのもののように詠まれているが、どんな川なのかあわれに思われる。
大井川。音無川。七瀬川。
耳敏川。また何事をりこうぶって聞いたのだろうと思うとおかしい。
玉星川。細谷川。五貫川・沢田川などは、催馬楽などを思い浮かべる。
名取川、どんな名を取ったのだろうと聞きたくなる。
吉野川。天の河原、「七夕の織姫に宿を借りよう」と在原業平が歌に詠んだのも面白い。
枕草子 第七十一段:
(原文)
ありがたきもの。
舅にほめらるる婿。また、姑におもはるる嫁の君。
(現代語訳)
滅多にないもの。
舅に褒められる婿と、姑にかわいがられるお嫁さん。
枕草子 第百二十二段:
(原文)
はしたなきもの。
他人を呼ぶに、「わがぞ」とさし出でたる。
物などを取らするをりは、いとど。
おのづから、人のうへなどうちいひそしりたるに、幼き子供の聞き取りて、その人のあるに、いひ出でたる。
(現代語訳)
気まずいもの。
他の人が呼ばれたのに、自分だと思って出ていったこと。
それが物を頂く時ならば、なおさら気まずい。
人の噂話や悪口を言っているのを、小さな子供が聞いていて、それを本人がいる時に話してしまうこと。
まとめ:清少納言の枕草子は日本三大随筆に選ばれた「をかし」の文学だった
清少納言の枕草子は、日本三大随筆に選ばれた日本最古の随筆でした。同時代の作品『源氏物語』と比較されることが多く、源氏物語は「あはれ」の文学、枕草子は「をかし」の文学だと言われています。
今回の内容をまとめると、
- 清少納言の枕草子は日本三大随筆に選ばれた日本最古の随筆作品
- 清少納言の内容は、清少納言が自身の宮廷生活を振り返りながら、感じたことや見たことなどを主に書いている
- 枕草子は、清少納言が仕えていた定子から紙をもらったことがきっかけで書き始めた
- 清少納言は枕草子を、最初は公表するつもりがなかったが、左中将・源経房によって広められた
枕草子の内容を見ていると、現代の私達にも多く共感できるようなところが存在します。これだけ長い年月を超えても共感できるような文章を書ける清少納言は、やはり知性が高かったと言えるでしょう。